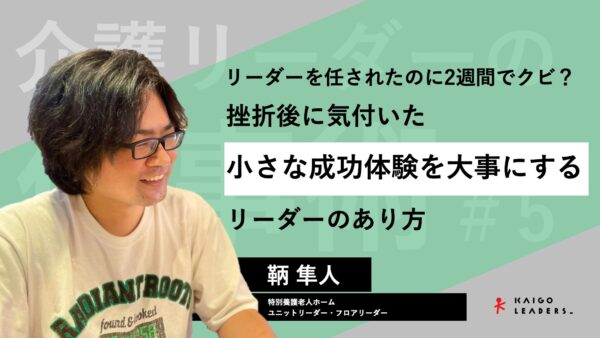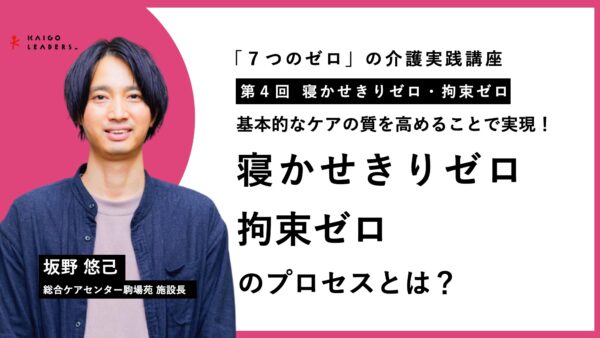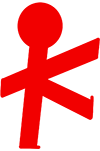
2030年、約160万人が亡くなる「多死社会」をどう描く?命と向き合い、自己満足の看取りケアから脱却する。(PRESENT_17 高山 義浩 前編)

日本社会は、2008年に人口のピークを迎え、緩やかな人口減少社会に突入しました。
これからは高齢化の進展と共に、死亡者数も増加していき2000年には約96万人だった死亡者数は、2017年時点で約134万人に、2030年には約160万人という「多死社会」が到来すると言われており、安心して最期の時を迎える「看取り」の場が不足するということが、社会全体の大きな課題となっています。
そんな超高齢社会における「看取り」が今回のPRESENTのテーマです。
これは介護・医療に携わる人でなく、この社会で暮らす全ての人にとって大切なテーマであり、誰もがその答えを求めています。
今回のゲストである高山義浩氏は、沖縄県立中部病院地域ケア科を立ち上げ、病院と地域包括ケアシステムの連携強化に取り組んでいらっしゃいます。また、厚生労働省において、高齢化を含めた日本の社会構造の変化に対応する地域医療構想の策定支援に取り組まれ、海外の地域医療現場も多数経験されています。
私たちは今後間違いなくやってくる「多死社会」とどう向き合うべきなのか。高山さんのお話からは、そのヒントが多くありました。
“点”ではなく“線”のコミュニティをつくる。
高山さんは冒頭、沖縄の自然と地域コミュニティについて語り始めます。「自然豊かな島で子供も老人も元気に過ごしている」と。そして自然が豊かということ以外にも、みんなが元気であることの大きな要因があるといいます。
私がいる地域には、「ハンタ道」という昔から生活道として利用されてきた道があるのですが、その道は車の乗り入れが禁止されていて、お年寄りに優しいゴムの道と、子供の大好きな芝生の道が並走していて、子どもたちが自由に道に駆け出すことができます。その道が世界遺産の中城城につながります。
高山さんは、子どもたちやお年寄りが自由に過ごせる「道」がコミュニティの機能を果たしていると考えます。
地域の人が集うコミュニティスペースは、全国色々なところで作られていますが、“点”であることが多いと思うのです。それを「道路をコミュニティスペースにする」という、いわば“線”にしたというのは、他の地域でも取り組まれて始めている試みです。おかげで人口も増え続けています。
コミュニティが点在するのではなく、線として「つながる」ことで、交流が活性化するということでしょうか。これによって、子供もお年寄りも自然と交わることができる環境が生まれるそうです。
延命治療はだれのため?地域医療の苦悩。
沖縄は長寿で知られています。白寿(99歳)のお祝いを、街をあげて盛大にパレードをしている地域もあります。そんなお祝いがあると、「長生きはしてみるもんだなあ」と感じるのだそうです。そう思える地域作りが、高齢社会において大事なのではないかと思います。
しかし、その一方で、実は胃ろう(口から食事を摂るのが困難な方が、栄養剤を胃に直接注入するために開けた穴のこと)からの栄養補給をすることで生きていられる方の数が全国ダントツ1位なのです。これは一体どういうことなのか。
胃ろうや点滴、心電図のモニターなど色々なものにつながれて、本人の意思もわからない状態で生き永らえることが、地域の人たちが望む姿なのか、地域医療に与えられたミッションなのか、医師たちも苦しんでいます。
長寿県と知られる沖縄では、意外にも胃ろうの実施率全国1位という事実がありました。そこにはどんな背景と想いがあるのでしょうか。
命と向き合う高齢者に敬意を持ち、語り合う。
沖縄において、私の外来に通っている80歳以上の独居の方全員からリビングウィル(体調など急変した際にどうして欲しいかなどの意思表示を確認すること)を確認したんです。そうすると意外にも、多くの方が延命治療を望まれていました。
今の高齢者の世代の方は、戦争による、戦闘、空襲、原爆、貧困などの命がけの苦難を乗り越えた方々であり、『戦争で家族を亡くして、その分までしっかり生き切らなきゃねえ』と思って生きてこられた方が多いんです。
かつて命と向き合った方が、いま死を迎えるにあたって再び命と向き合う。そんな方への敬意と、命を語り合う姿勢を私たちの世代が持っておかないと、こちらの自己満足による看取りケアになりかねない。“過度な延命なんて”、“胃ろうなんて”、などと安易に決めつけてはいけないんです。
いま現在高齢者の方は、なんらかの形で戦争を経験されています。特に沖縄は激しい地上戦も行われ、多くの民間人も犠牲になっています。そんな中を生き抜いてこられた方にとっては、“生きることの意味”が現代の戦争を知らない世代とは違うのかもしれません。
医師や医療者は、病院に運ばれてきた患者さんには全力で治療に当たります。病院にきたということは、“なんとかして欲しい”ということだからです。どういう死を迎えたいかは、病院に搬送する前に決めておかなければならないんです。
高山さんは、私たち一人ひとりが自分や家族が「どう生きたいか」をしっかりと考え、話し合っておくことの重要性を訴えます。
どんな時代を生きて、どんな想いで生きてきたのか、そしてどんな想いで死にたいのか。目の前のお年寄り一人ひとりの想いと真摯に向き合うことが、何より大事なことなのでしょう。
医師には、退院の判断は難しい。多職種連携の重要性。
高山さんは、医療における地域包括ケアの課題のひとつとして、“病棟の看護師”が地域に入り切れていないことを挙げておられます。
私たちは、退院時のカンファレンスは、自宅で行うようにしています。
“これから暮らす”環境の中で話し合わなければ、直面する課題について議論できないからです。そして病棟の看護師も参加させます。そうすると病院での問題点を、この家の環境ならどう対処できるかについて、現場で具体的に話し合えるのです。
また、退院するかの判断は看護師にやってもらいたいと思っています。なぜなら医師は回診などの限られた時にしか接していないし、病状の経過や検査データに基づいた判断はできるけど、「家で生活できるのか」などという判断は難しいからです。実際に食事やトイレ、入浴などに関わりながら、また愚痴などを聞いたり、家族とも沢山話をしている看護師こそ、退院できるかどうかの適切な判断ができると思うからです。
医師は退院の判断なんてできないんです。そして、できないのにやっているから問題が起こるんです。
高山さんは謙虚に、そして冷静に職種の領分と、できること・できないことを分析されていました。そして、あくまでそれは患者さんのためを考えた視点です。
お年寄りの想いに寄り添う、そのために医療・介護・看護、そして家族がどのように連携していくのか。実際のエピソードを紹介して下さいました。
生きるために足を切るのか。母と子の想いに寄り添う。
戦争中にハブに噛まれたことにより右腕を切断した高齢の女性がいらっしゃいました。
その方は当時高齢者施設に入所されていたのですが、発熱と吐き気で受診されてきました。検査してみると感染症とわかり、それは左足の骨まで達して既に腐骨化していたんです。骨が腐ってしまうと点滴をしても血流が届かないので治せない。切断するしかない。
息子さんも交えて話し合い、下腿切断という方針となりました。息子さんは「切ってやってくれ」と、本人は「わかりました」と言っていました。
そんな折、施設の介護士さんがお見舞いに来てくれたんですが、その介護士さんにご本人が「本当は足を切りたくない』と本音をこぼしていたというんです。
教えてくれて本当に良かったです。私たちは、そうとも知らずに、この方の足を切ってしまうところでした。患者さんも医者が言うならと、つい「うんうん」とうなずいてしまいがちです。でも、患者さんが本音を打ち明けられるのは、正論を言う医者じゃないんです。今回の彼のように介護士には、生活の中で密にコミュニケーションを取っているので、正論とは別の“暮らしの視点”で、こうしていきたいという本音を引き出す力がある。そのことに改めて気づかされました。
お年寄りの生活の支援をすることこそが介護の専門分野。それ故に本音に触れる場面は多くあります。そしてそのことは、実は介護の現場でしかできないことなのではと感じました。
地域医療を展開するにあたって、医療者だけで連携していてはダメなんです。今回のケースでは、切るか切らないかの意思決定プロセスを本人に決めさせるのではなく、“本人と共に考えていく”ということが必要なんだと思いました。
そこで高山さんは、介護士と一緒に、彼女がどうしたいのか、改めて聴いてみることにしました。すると彼女は語り始めます。
「沖縄戦の時、山へ逃げているとハブに右腕を噛まれて動けなくなってしまった。
右腕は大きく腫れあがって意識も朦朧として、、、そこを米軍に捕まってしまったのです。そして私の右腕は米軍の軍医によって切り落とされてしまった。私の断りもなしに、切り落とされてしまった。私はこのことが本当に辛かった。
もし私に右腕が残っていたら、こんなに辛い人生ではなかった。商売をしていたが、もっと上手くできたかもしれない。お裁縫もできただろう。右腕がないことで私の人生はとても苦しいものになった。だからもう二度と、誰にも私の体を切り落とさせはしない。」
その一方で息子さんは、「母が生きるためなら、足を切ってやってほしい」と考えています。そしてその想いを語られました。
「沖縄戦の時、7歳でした。母と一緒に逃げていたが、母がハブに噛まれてしまった。
ずっと付き添っていたのですが、母に『私はもうだめだ。あなた一人でも逃げなさい。』と言われて、母親を置いて逃げました。しかし米軍に捕まり収容所に入れられたのですが、そこで右腕を切り落とされた母と再会したのです。
右腕のない母を見て、私は誓ったんです。もう二度と、母を見捨てたりしない。私がしっかりケアしていきますから、足を切ってやって下さい。それで母が生きられるのなら、そうして欲しいんです。母は強い人です。」
「もう二度と身体を失いたくない」という女性の想い。
「もう二度と母を見捨てない」という息子さんの想い。
いったいどちらの想いを聴けばいいのでしょうか。
もし、あなたが医療者であったなら、どんな決断をするのでしょうか。
高山さんは、息子さんにこう伝えました。
お母さんをもう二度と見捨てたくない、という想い。その想いを伝えたことはありますか。今こそ、それを伝える時なんじゃないですか。その想いを伝えてください。お母さんはお母さんの想いがあるようです。医療者を間に挟むことなく、じっくり話し合ってきてください。
そうして母子は長く話し合ったそうです。
お二人が出した結論は、
“足は切らない”でした。
高山さんたち医療チームは、その想いを尊重し、支えるための体制を整えていきました。
切らないという方針のもと、治療方針と施設に戻ってからの訪問診療や介護についての計画を立てました。比較的順調に経過し、無事退院されまして、その後も長く生きて下さったようです。退院後は直接関わる機会もなくなっていきましたが、最終的には感染症以外の理由により、お亡くなりになられたと伺いました。
介護は生活の支援。生活の積み重ねが人生。介護とは人生の支援とも言えるのではないでしょうか。
そこにある当事者の想いを横に置いては、人生の支援はできません。
お二人の想いに寄り添い、真摯に向かい合ったおかげで、きっとお二人にとって納得のいく“最期”を迎えることができたのではないかと思います。
大切な家族の最期の時。人生に一度きりの“その時”に、悔いを残して欲しくない。そのために、当事者の想いを橋渡しをして、ともに考えていくことが、医療・介護従事者にとって、とても重要なのだと考えさせられる、貴重なお話でした。
後半では、海外の事例も交えながら、地域で最期の時を看取る仕組みづくりについてご紹介します。
(後編に続く)
ゲストプロフィール
高山 義浩(Yoshihiro Takayama)
沖縄県立中部病院感染症内科・地域ケア科 医長
群馬大学医学部非常勤講師、神戸大学医学部非常勤講師
琉球大学医学部非常勤講師、日本医師会総合政策研究機構非常勤研究員、
沖縄県地域包括ケアシステム推進会議医療介護連携部会長、うるま市高齢者福祉計画策定委員会委員。
沖縄県立中部病院に地域ケア科を立ち上げ、退院患者のフォローアップ訪問や在宅緩和ケアを開始。その後、厚生労働省医政局地域医療計画課において高齢化を含めた日本の社会構造の変化に対応する地域医療構想の策定支援に取り組む。現在は、ふたたび沖縄県立中部病院に戻り、在宅緩和ケアと地域包括ケアシステムの連携推進に取り組んでいる。
開催概要
日時:2018年11月23日(金・祝)
会場:神楽坂Human Capital Studio
PRESENTについて
2025年に向け、私たちは何を学び、どんな力を身につけ、どんな姿で迎えたいか。そんな問いから生まれた”欲張りな学びの場”「PRESENT」。
「live in the present(今を生きる)」という私たちの意志のもと、私たちが私たちなりに日本の未来を考え、学びたいテーマをもとに素敵な講師をお招きし、一緒に考え対話し繋がるご褒美(プレゼント)のような学びの場です。
写真撮影

近藤 浩紀/Hiroki Kondo
HIROKI KONDO PHOTOGRAPHY